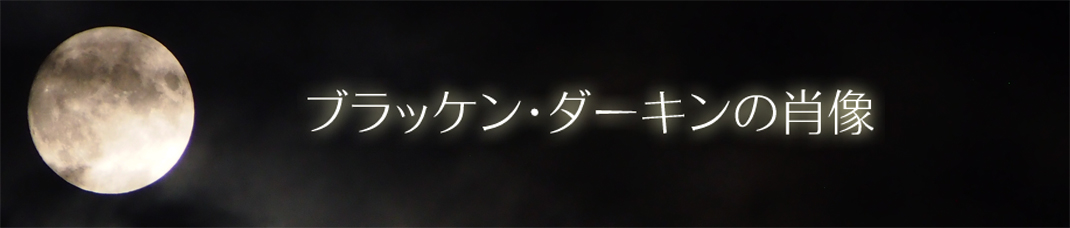『さかしま』(ユイスマンス)が「デカダンスの聖書」なら、『悪魔のような女たち』(バルベー・ドールヴィイ)はデカダンスの何だろうかと考えてみたが、適当な言葉は訳者中条省平の解説にあった。「十九世紀末のフランス文学が生んだ奇形的デカダンスの見本帳」だ。
『さかしま』の第十二章の最後の方にバルベー・ドールヴィイについて書いてある。
いま自分が整理したすべての書物のうちで、その思想と文体とがあの腐肉の味、あの死斑、あの爛れた表皮の美しさを示しているのは、やはりバルベエ・ドオルヴィリイの作品だけだな、と彼は心の中で考えた。熟れすぎて腐る一歩手前の、こんな不健康な魅力こそ、彼が古代のラテン文学や修道院文学の頽唐派のうちに、こよなく愛した味わいでもあった。
デカダンスは何となく背徳的でお耽美な雰囲気というのではなく、「熟れすぎて腐る一歩手前の」というところが重要だ。古い本だから今読むとたいしたことないということはなく、今読んでも充分不道徳だ。
原文を読んだわけではないがフランス語は文を修飾していくらでも長くできる言葉で、皮肉の効いた比喩や言い回しなどフランス語の雰囲気が伝わる訳は格調高く、しかも読みやすい。こんな日本語を使いたいものだ。ストーリーだけではなく語りがいいので、何度でも読みたい。
六つの短篇はどれもいいが、一発目「真紅のカーテン」はインパクトがあった。「バカ」でも何でも何か言葉があればコミュニケーションが成立する。だが、女の黙り込みにはどうにも対処のしようがない。特に嘘と黙り込みの複合技は地獄の苦しみだ。何が真実が判らず、いつ終わるか判らないからだ。私にはこの小説のような劇的な経験はないが、それは解る。昔から女とはそういうものか。次の一文など、客観的に読むと笑ってしまうが、本人は相当苦しんでいる実感が伝わってくる。
たしかに、女は男を多かれ少なかれ下僕扱いするものだと承知してはいますが、これほど酷いとは!!