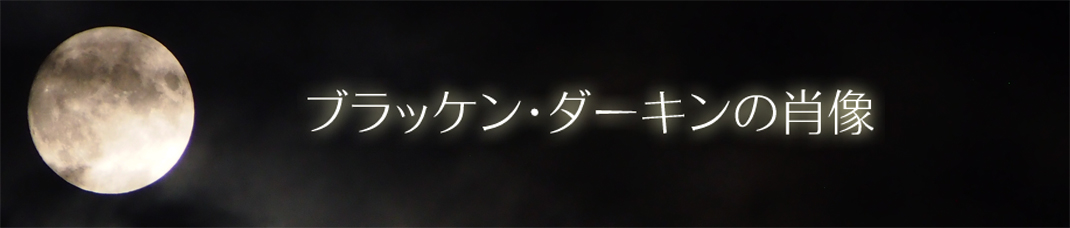『オペラ座の怪人』(ガストン・ルルー 1910)はフランケンシュタインの怪物と近いのではないだろうか。映画の印象ではなく、原作『フランケンシュタイン』(メアリー・シェリー 1818)では怪物の醜さについて、何度も描写されている。善良でありたいと思いながらも醜さゆえに迫害されて怪物になるところも似ている。オペラ座の怪人は、仮面に触れない限りは何も危害は加えないとクリスティーヌに云った。だが、それだけの共通点ではまだ弱い。
《反逆者 モンスター》
次にピンと来たのは「モンスター」という言葉についてだ。週刊朝日世界の文学7に載っている風間賢二の文章によると、「モンスター」は19世紀初頭までは「見せる」とか「警告する」という意味で、おぞましい異形の姿は凶事の前兆であり、神の教えに背いた罰とみなされていた。人造人間がモンスターと呼ばれる所以は醜怪な容姿にあるのではなく、創造主に対する「裏切り」や「反逆行為」にある。危険な極地探検に出立した船乗りウォルトン、自然の摂理(神)に背いて生命の神秘を究めようとしたフランケンシュタイン、フランス政府を裏切ったド・ラセー一家(怪物が語る物語に登場する)もまた、モンスターなのだ。
フランケンシュタインの生命創造への野心には、知識に対する情熱により悪魔と契約する『ファウスト』の要素もある。オペラ『ファウスト』は『オペラ座の怪人』に登場する。クリスティーヌがカルロッタの代役で歌い喝采を浴びるところ、カルロッタがカエルの声を出しシャンデリアが落ちるところという重要な場面で。怪人はクリスティーヌを求めるファウストであると同時に彼女を導くメフィストフェレスでもある。そして怪人自作のオペラは「勝ち誇ったドン・ジョヴァンニ」。『ドン・ジョヴァンニ』もまた神への反逆者だ(参照 「ドン・ファンは何に勝利したのか」)。
《なぜ怪物は黄色いのか》
『フランケンシュタイン』第五章、怪物に生命が与えられ動き出すところは、「その物体の鈍く黄色い目が開くのを目にした」、「黄色い皮膚は、その下にある筋肉や動脈の動きをほとんど隠すことはなく」となっている。ヨーロッパ人の死体のはずなのに何故黄色なのか。怪物は黄疸にかかって生まれたという説がある(参考文献 『批評理論入門 『フランケンシュタイン』解剖講義』 廣野由美子 中公新書)。
ここでまた『オペラ座の怪人』を連想した。第一章、道具方主任ジョゼフ・ビュケは怪人について「骨に張りついた皮膚は太鼓の革みたいにぴんとして、白というより嫌らしい黄色をしている」と語る。怪人の目は暗いところで金色に光るという描写も何か所かある。実際に黄疸患者の目が光るなどありえないが、フィクションなので黄色い目からイメージしたものとは考えられる。
ガストン・ルルーが『フランケンシュタイン』の影響を受けたという証拠はない。だが、怪人がクリスティーヌに仮面を剥がされたときに「わたしは体中が屍肉でできているんだ」と云ったり、『オペラ座の怪人』より後になるがルルーは人造人間が出てくる小説を書いている(参照 「『吸血鬼』 『オペラ座の怪人』原作者ガストン・ルルーのアンドロイド小説」)。何か関係がありそうな気がする。