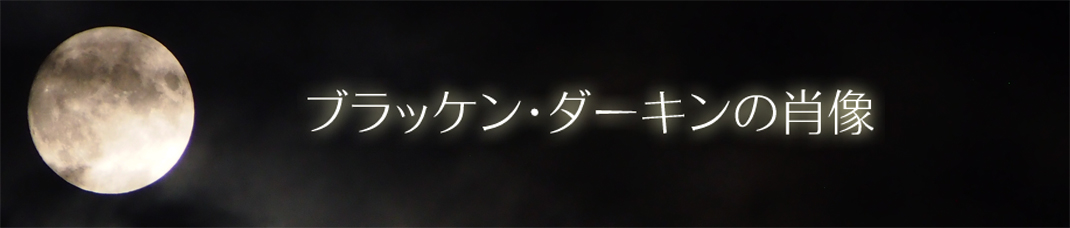二つの大戦の間のアメリカの様々な事件について書かれた『アスピリン・エイジ』という本がある。1920年代、30年代のアメリカは熱病に冒されたようにさまよった時代で、すべてを癒してくれる万能薬を探し求めたが、結局与えられたのはアスピリン程度のものにすぎなかったことから編者のイザベル・レイトンが名づけた。
私はこのあたりの時代に興味があるので買ってみた。買ってから気づいたが、岩波版は全訳ではないのだ。ハヤカワ文庫の方が全訳で、安さにつられて岩波版を買ったのは失敗だった。だが、岩波版はデザインも旧漢字も味のある古書で、売り払うのももったいないような複雑な気分だ。
1951年の岩波版訳者あとがきによると、当時のアメリカは強烈に自己批判が行われる国だったらしい。政権や戦争指導者の失敗を追及するためには重要な軍事機密までもが暴き出され、「くさいものにはふた」という言葉はアメリカ人のヴォキャブラリーにはないという。訳者木下秀夫は『マッカーサーの謎』(ジョン・ガンサー)を引用して、次のように書いている。
最近アメリカを訪問した日本のある使節団の団長が、出発に先だち、マッカーサー元帥のところに挨拶にゆくと、元帥はその団長に「アメリカの悪い面もよく見てきなさい」といってかれを驚かせた。
反省と自己批判とを失ったとき、人はその進歩をとどめる。国家の場合も同じである。ナチのドイツも、ファッショのイタリアも、この自己批判を失っていた。「天壌無窮」「八紘一宇」の軍閥日本も、この自己批判を失っていた。こうした国では、たとえ一時的、表面的には進歩と見えるものがあったにしても、それは要するに破滅に向かっての行進でしかない。歴史がこれを証明した。
『アスピリン・エイジ』をもじって薬で現在の日本を表すなら、「バカにつける薬はないエイジ」と云える。