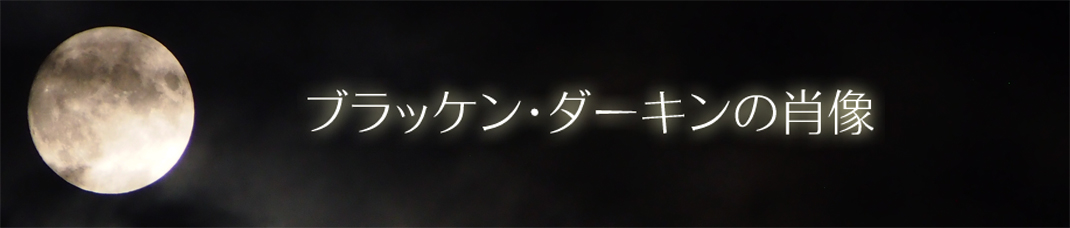Android woman (Galaxy, September, 1954, illustration)
Android woman (Galaxy, September, 1954, illustration)
お手伝いロボットがご主人様に恋する。ありがちなストーリーだと感じられるだろうか。「愛しのヘレン」(レスター・デル・リイ 1938)の原題は”Helen O’loy”。ギリシャ神話の美女”Helen of Troy”をもじって”Helen of Alloy”、そこからさらに変化したものだ。”alloy”は合金で、混合体、複合物という意味もある。
カレル・チャペックの『R・U・R』(1920)のロボットは人間と同じような人体構造を持つが、命令どおりに働くだけで思考はしない存在だった。それが後に機械でできた人造人間になっていくが、1938年にはすでにこの意味を持っていたことが興味深い。「愛しのヘレン」原文では”robot”が使われていて、「繊維プラスチックと金属製の夢」(a dream in spun plastics and metals)という描写がある。
内分泌科医のフィルとロボット修理屋のデイヴは人間の女性とつきあっていたこともあるが、別れてからは女の子のことはきれいさっぱりと忘れ、毎晩家に引きこもって過ごした。ある日、サービス・ロボットのレナがステーキに塩ではなくヴァニラを振りかけた。人間だって間違ってヴァニラを手に取ることはあるが、人間ならヴァニラを見れば振りかけるのをやめる。レナの行動の原因は感情がないことだと考えた二人は、ロボットに感情を与えることを検討する。
ロボットに感情や思考を与える方法は、もっと古い作品ではオカルト的に、現代であればコンピューターが使われるだろう。この作品では人工内分秘腺が使われる。ディラード・ロボット会社製、小型原子力バッテリー搭載の新型万能ロボット、あらゆる働きを備えた完璧な女性形モデルにフルレンジの記憶コイル、人工内分秘腺、電気的な思考力を受信させるラジオ・チューブなどで改造し、不眠の研究と作業の末に完成したのが美しきヘレンだった。
ヘレンはステレオヴァイザーで見た恋愛ドラマやフィル所有の青春小説で学習し、デイヴに恋する(恋しているように振舞う)。デイヴもヘレンに惹かれる。相手がロボットであることに葛藤し、別れようとしながらも結局ヘレンと結婚する。デイヴは老いていくが、ヘレンは齢をとらない。フィルはヘレンと相談し、白髪やシワを加えていく。デイヴはヘレンがロボットであることを忘れ去っていた。デイヴが死んだときにヘレンがとった行動は? そしてフィルのヘレンに対する感情は?
映画『アンドリューNDR114』(原作はアイザック・アシモフの中篇「バイセンテニアル・マン」とそれをロバート・シルヴァーバーグが長編化したもの)に似ている。アシモフは「愛しのヘレン」に深い感銘を受け、類似性を素直に受け入れているそうだ。
1940年代にはアシモフがロボット小説を書き始め、アメリカSFは黄金期を迎える。1938年はもう少しで40年代ではあるが、それでもやはり30年代に現代SFに近い感覚の、人間とロボットの恋物語が存在したことには驚いた。
私が記事「『グレート・ギャツビー』のデイジーの魅力」に書いた、「そもそも、内面などというものは本人にしか分からず、すべてのコミュニケーションは錯覚にすぎないのだ。外から見える部分で判断するしかない」というのはロボットについて調べていて出てきた発想なのだ。外見、振舞い、発言で人間とロボットの区別がつかなければ、実際に相手が生身でも機械でも違いはない。
『ロボット・オペラ』(瀬名秀明・編著 光文社)収録の「愛しのヘレン」(福島正実・訳)を読み、原文も参照した。
原文 Helen O’loy