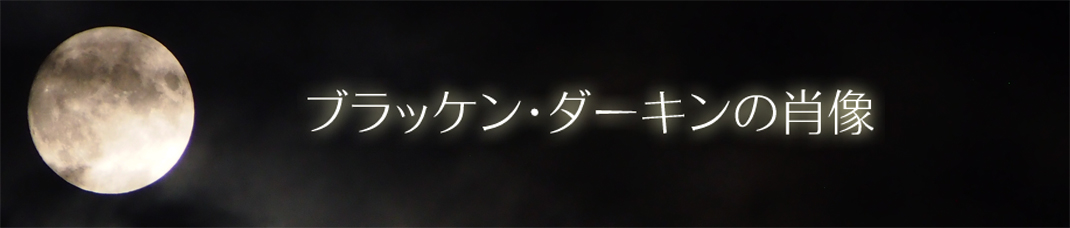フィッツジェラルドはミステリ風、ファンタジー風の小説も書いている。『グレート・ギャツビー』にしてもリアリズムのようでいて、ちょっと風変わりなところもある。 ファンタジーが多めの短篇集『ベンジャミン・バトン』(角川文庫)の解説によると、フィッツジェラルドは大の読書家で通常の文学作品だけではなくエンタテインメント系も吸収していて、ガストン・ルルーも読んでいたそうだ。
ガストン・ルルーの『吸血鬼』(『ゴシック名訳集成 吸血妖鬼譚』収録)は、私の好きな吸血鬼、アンドロイド、『オペラ座の怪人』の要素がひとつになった1924年の仏蘭西の小説だ。凄すぎる。原題は”La Poupée Sanglante ” (血まみれの人形)で吸血鬼そのものは出てこないが、きちんとした吸血鬼伝承が出てくる。
ヒロインの名前は『オペラ座の怪人』と同じクリスチーヌ。クリスチーヌに恋するのは顔は醜いが美しい詩を書く美術製本家ベネヂクト・マソン。二人はあるきっかけでクールトレエ侯爵の図書館で働くことになるが、この侯爵が曲者だ。
クリスチーヌの父親は時計職人で機械的部分を担当、クリスチーヌの婚約者は医科大学の解剖助手で生理的部分を担当して人造人間ガブリエルを作っている。この辺の設定はアンドロイド好きの私としては嬉しくなってくる。ガブリエルは美しい顔で、フランス大革命当時の服装で、言葉が話せない。「殺人機」と呼ばれ、ナイフで刺してもピストルで撃っても怪力で暴れまわる様はターミネーターのようだ。リイル・アダムという地名が出てくるあたり、『未來のイヴ』も念頭にあるのかもしれない。
ネタバレになるので書かないがびっくりするような事件が起こり、仮面で醜さを隠すのと似た状態、ガブリエルにベネヂクトの心が宿る。殺人教団にクリスチーヌがさらわれ、色々巻き起こる。
登場人物が多くてゴタゴタした印象なのは古い小説なので仕方ないのかもしれない。クリスチーヌ救出やガブリエルの末路についてもっと書いてあればとも思うが、あっさりしている分、色々想像できる。かなり猟奇的なロマンティシズムだ。
原文のPDF
目次を見ると多分『ゴシック名訳集成 吸血妖鬼譚』収録の「吸血鬼」は続編の”La Machine à assassiner”を含めた訳のようだ。ありがたいことだ。「殺人機」は意訳かと思っていたが、直訳だったのか。
そしてこの作品は1976年にドラマ化されている。私はダウンロードしたが、キャストやロケ場所はイメージ通りで、陰鬱でいい雰囲気だ。クリスチーヌの婚約者は原作では髪が薄くて背が低いと書いてあるが、ドラマではかっこいい。全部通しては見ていないが、ちらっと見ただけで、ああ、あのシーンだと判る。コルビエールの水郷というのも、こういうところなのかと分かった。今調べたら、コルビエールは人口26人らしい。
« La Poupée sanglante »
同じように吸血鬼そのものは出てこないが吸血鬼伝承が出てくる機械趣味の仏蘭西の小説に『カルパチアの城』(ジュール・ヴェルヌ 集英社文庫)がある。
《関連記事》