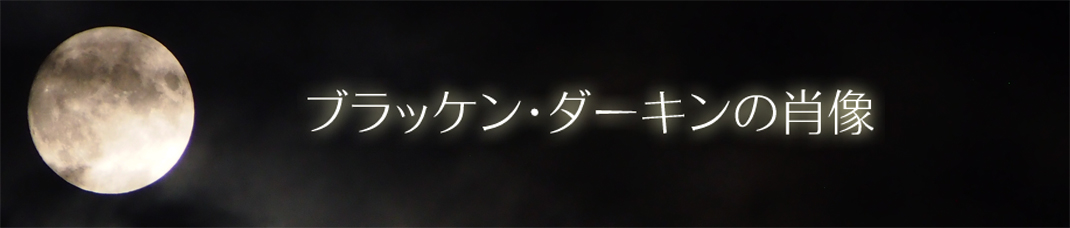『神々の黄昏』(エレミール・ブールジュ 1884)はワーグナーのオペラを踏まえたタイトルや表紙の黄金の馬車の写真から重厚な作品かと思いきや、読み始めたら次から次へと事件が起こり、夢中になってしまった。冒頭は人物紹介のようだが、そこを過ぎると面白くなってくる。
『さかしま』(J・K・ユイスマンス 1884)の珍奇、奇想、『ドリアン・グレイの肖像』(オスカー・ワイルド 1891)の頽廃、ジャン・ロランやバルベー・ドールヴィイの俗悪、ゴシップ誌なみの下世話さもある。建物や調度の大げさなまでの華麗さ、細かい心理描写やエスプリの利いた発言に何度も笑った。再読したい。
史実と虚構が入り交じっている。1866年、プロイセンに侵攻されたブランケンブルク公国君主のカール・デステ大公はパリに亡命する。そこでの一族や側近たちの恋と野望の渦巻く一大絵巻。プレイボーイでのちにギャンブル狂になる長男フランツ、二人で一人かのごとく深く慕い合っている次男ハンス・ウルリッツと長女クリスチアーネ、不良だが大公お気に入りの三男オットー、病弱な次女クラリベルという、個性的な庶子たちに加え、側近たちもかなり強烈だ。大公に気に入られ道化師から寵臣にまで成り上がるイタリア人、ジョヴァン・アルカンジェリ(実は間諜の技術も持っている)、ジョヴァンの妹でクラリベルの養育係でフランツと恋の駆け引きをするエミーリア、大公の愛妾となりハンス・ウルリッツとクリスチアーネの近親相姦をそそのかし、大公と別れたあとはオットーと愛し合い陰謀を企てる歌姫ジュリア・ベルクレディという濃い面々。アルカンジェリとベルクレディは憎み合っている。かなり滅茶苦茶でありながらサスペンスあり、孤独の哀愁もある。
解説に、ルキノ・ヴィスコンティ監督の『ルートヴィヒ』などに通づる題材で、激動する世情に翻弄される王侯たちの歴史絵巻とある。確かに最終章に反資本主義的な文章はある。だが、この愚かなる人々は歴史の変化などなくても勝手に滅びたであろう。