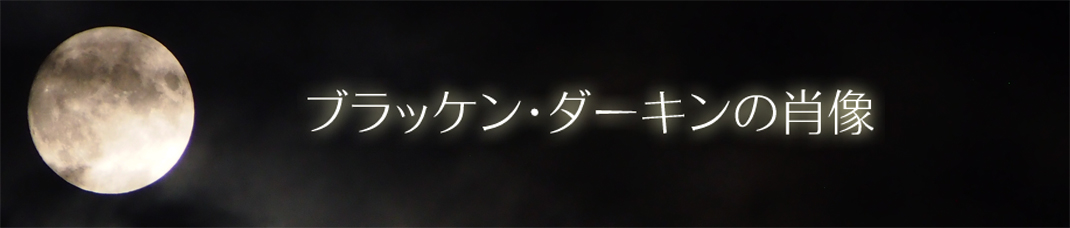耽美で芸術性が高く、映画として面白いのは『ルートヴィヒ』(ルキノ・ヴィスコンティ監督 1972)だが、『ルートヴィヒ』(マリー・ノエル ピーター・ゼアー脚本・監督 2012)は堅実なつくりでドイツの意地を見せたというところだろうか。山や森の自然風景や城、馬車の映像が豪華で、ルートヴィヒ即位前の不安、政治、戦争、フランスとの関係、オペラ上演、婚約破綻、自殺未遂、国内視察、築城などが分かりやすく描かれている。
ルートヴィヒ役は繊細な感じで時々威厳を見せていてよかった。不満は青年期、晩年ともに目力が足りないところだ。実在のルートヴィヒの肖像画や写真では眼がイッちゃっている。
狂王としてではなく普通の人間として描こうとしたのかもしれない。あとはグロッタ(人工洞窟)が出てこないところくらい。
「男っていつまでたっても子供ね」、「これだから女ってやつは」という感じで面白いのは、真剣にオペラを観ているときに婚約者ゾフィーから接吻され、邪魔されたルートヴィヒが怒り出すシーンだ。一般人でさえ、仕事でも趣味でも資格の勉強でも何でもいいが、何かやろうと思ったら異性にかまけている暇などない。いわんや国王をや。
ゾフィーの姉エリザベートから叱られて「愛など存在しない」と主張するルートヴィヒ。金持ちはもっと金儲けしようと戦争をやりたがる(現代日本も同様)のに戦争を避けようとしたルートヴィヒ。狂王どころかまったくもって正常である。