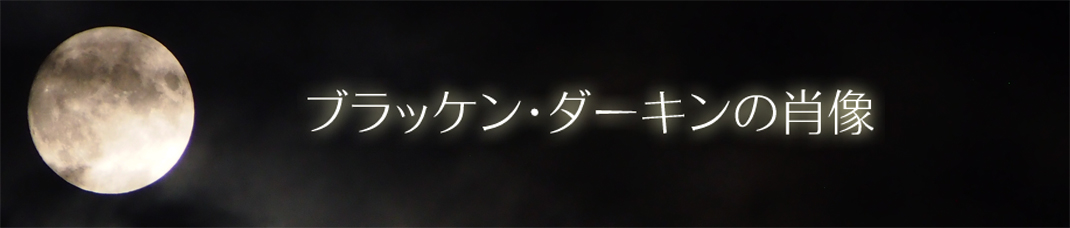1920年代終わりの浅草小説が『浅草紅団』(川端康成)なら、1920年代初めのは『鮫人(こうじん)』(谷崎潤一郎)だ。これを読もうと思って借りた『潤一郎ラビリンス Ⅸ浅草小説集』(中公文庫)に収録されている短篇「襤褸(らんる)の光」を先に読んだ。
襤褸とはボロのこと。浅草公園を徘徊する女乞食を孕ませたのは誰か。噂が色々流れているのだが、語り手はそれが画家の友人Aであることを知っている。
Aは美を見抜き、スケッチする天才を持っているものの、技術を身に付ける根気が欠けていて、裕福だったが怠け癖から貧乏になる。「妻と云うものは、商人や政治家には必要なものかも知れないが、藝術家には何の足しにもならないものだ」という、笑ってしまうくらい至極もっともなことを口走るAが、どのようないきさつで女乞食のところへ行くのかが語られる。
文字だけ読んでも、美しそうな描写はまるでない。醜さの中にも若さや、一部のパーツのみの美を見いだすことがあるのだろう。
この題はボードレールが女乞食の美しさを歌った詩から取られている。この女乞食は実在の人物なのだが、それについてはまたいつか。
《追記》
本文に書いたボードレールの詩は『悪の華』の中の「赤毛の乞食娘に」だ。検索すれば訳しているブログもある。この娘は実在し、テオドール・ド・バンヴィルも詩集『鍾乳石』で「路上の小さな歌唄ひの娘」を詠み、著書でカルチエ・ラタンでギターを弾きながら唄って流し歩いていた、目の大きなかわいらしい娘について描写し、作品のきっかけになったことを述べている。
画家エミール・ドロワが描いた肖像画も残っている。(参考文献 『悪の華』岩波文庫)
 La mendiante rousse – Émile Deroy (vers 1843)
La mendiante rousse – Émile Deroy (vers 1843)
(2017年5月24日)