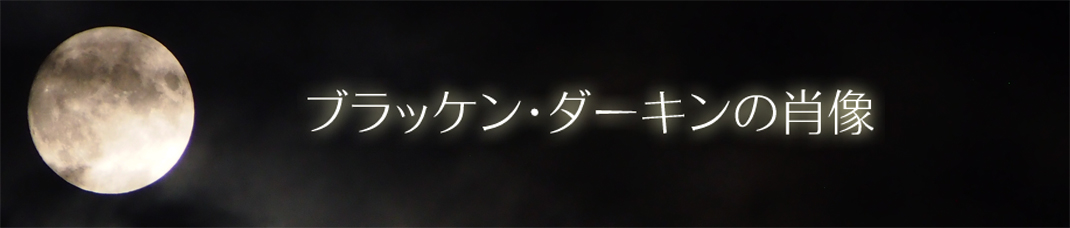私は基本的にフランス贔屓、怪奇なイギリスもドイツロマン派も好きだが、今はアメリカの『グレート・ギャツビー』に凝っている。『『グレート・ギャツビー』の読み方』(野間正二 創元社)によれば、ギャツビーはロマン派の嫡子なのだそうだ。フィッツジェラルドの両親はアイルランド系ということなので、神秘的なところがあるのかもしれない。
ギャツビーは、両手を天上ではなく、水平に差し出している。地上のものにさしのべられた両手は、ギャツビーがロマン派の嫡子であることを示している。天上の神ではなく、地上の女に憧れ、身をふるわせているからだ。 しかも、それがロマン派が愛した夜のことだからだ。ギャツビーは、昼の太陽の光のもとにあるあからさまな現実ではなく、夜の暗闇の彼方に光っている人工の光に憧れている。夜の闇の彼方にこそ、夢はありえるのだ。
何かを求めて、手に入らないというのは普遍的だ。それが身近な人間だろうと、舞台や音楽の人だろうと、架空の人物だろうと、人形だろうと、精神の動きには何の変わりもないし、身近な人間ならうまくいく可能性が高いかというと、そんなことは全く無い。
フィッツジェラルドはパリに滞在したことがあり、『グレート・ギャツビー』(1925)は、「ザ・グレート」のフランス語「ル・グラン」がタイトルに付いた『グラン・モーヌ』(アラン・フルニエ 1913)の影響を受けているらしい。こちらも買って置いてあってまだ読んでいないので、是非読みたい。