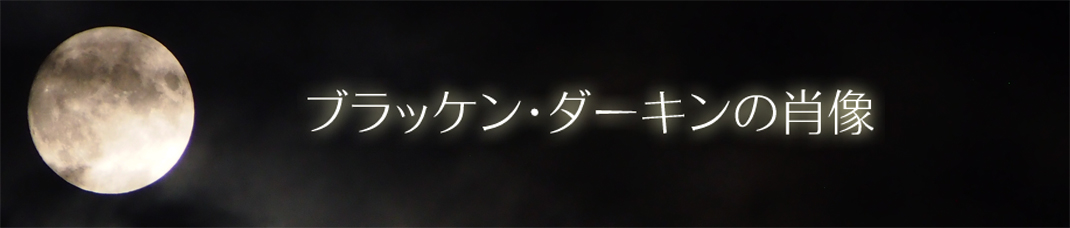映画『ダンシング・レディ』(1933)でダンサー役のフレッド・アステアが相方の女性に、自分のことを「スヴェンガリ」だと云っていた。「コンビで人気なのも俺のおかげなんだぞ」という程度の意味だ。アーチ・メイヨ監督、ジョン・バリモア主演の『悪魔スヴェンガリ』(1931)は音楽教授で眼で催眠術をかける怪人が女を意のままに操って連れ去り、歌手にする話で、それを踏まえている。
娘を知っていた男がスヴェンガリを追うところが『オペラ座の怪人』に似ている。あっけない終り方が古い映画らしい。 音楽のシーンあり、(舞台はパリだが)アメリカンジョークあり、愛されない悲哀ありの不思議な映画だ。CGはないのに室内の人物からカメラが引いて窓の外に出てパリの街を飛んで別の建物に入っていくカットがある。表現主義というほど曲がってもいないが、何となくリアルではない建物が面白い。
スヴェンガリの名前を再び見たのは『機械仕掛けの歌姫 19世紀フランスにおける女性・声・人造性』(フェリシア・ミラー・フランク 東洋書林)でだった。人造美女、独身者の機械のテーマを聴覚、声から考察した本だ。映画は見ていたが、その原作が『トリルビー』(1894)というイギリスの小説だとは知らなかった。作者はジョージ・デュ・モーリア(ジョルジュ・デュ・モーリエと表記される場合もあり)。是非読んでみたいが、邦訳はない。フランスのシャルル・ノディエに同名の小説があるが、別のものだ。
久しぶりに『悪魔スヴェンガリ』を見てみると、ヒロインのトリルビー役のマリアン・マーシュが随分フラッパーな感じだなと思ったが、これはおそらく催眠術にかかったときとの差を見せるためだ。顔も髪型も可憐でよい。原作は読んでいないが『機械仕掛けの歌姫』によると男性的でもあり、天使を思わせる姿でもあるということで、映画でも現代的な女性として描かれたのだろう。
『機械仕掛けの歌姫』は色々な文学作品を扱っているが、音楽が重要な要素の『トリルビー』が映画化されたということが、映画というメディア、トーキーの歴史に関わっているような気がする。
『ジャンク・フィクション・ワールド』(風間賢二 新書館)にも『トリルビー』について書いてあり、ジョージ・デュ・モーリア自身の挿絵も載っている。この本によると、催眠術の元になった療法を始めたのがオーストリアの医師メスメルで、彼はモーツァルトのパトロンでもある。ここでもまた音楽である。催眠術は19世紀の様々な小説に出てきて、『トリルビー』は大流行したそうだ。現在は帽子の種類にトリルビーの名が残っている。
『ジャンク・フィクション・ワールド』 に、『トリルビー』は『フランケンシュタイン』(メアリ・シェリー)のヴァリエーションで、元をたどればギリシア神話の「ピグマリオン」にたどりつくとある。『機械仕掛けの歌姫』では『カルパチアの城』(ジュール・ヴェルヌ)や『未来のイヴ』(ヴィリエ・ド・リラダン)、ホフマンの「砂男」、「クレスペル顧問官」などと並べて論じている。上記二冊では触れられてなく、時期は少しずれるのだが、音楽、ピグマリオニズムということで私はここに『オペラ座の怪人』(ガストン・ルルー)も加えたい。『オペラ座の怪人』を、クリスティーヌが催眠術にかかっているようであまり好きではないという感想を見たことがあるが、意外と正しい解釈なのかもしれない。