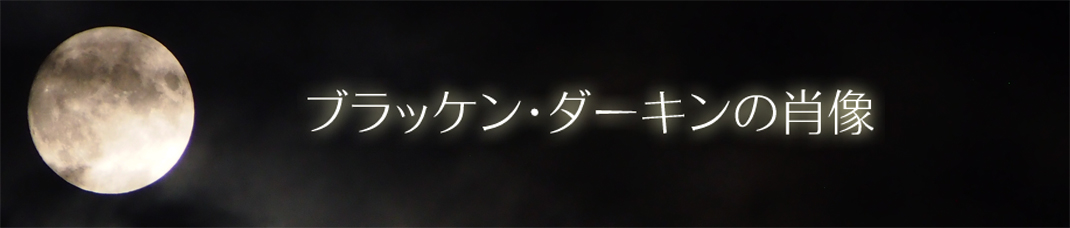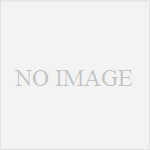『浅草紅団』(川端康成)などで読んだ浅草は、現代の私から見ると幻影の都市のように感じる。では当時の感覚ではどうか。「幻影の都市」(室生犀星)という小説がある。上京後の貧窮放浪生活から生み出されたそうだ。大正十(1921)年の作品なので、関東大震災や大恐慌の前だが、既に混沌と貧困がある。
川端康成は大阪、室生犀星は金沢出身だ。いづれも異邦人から見た都市文学なのだろう。
幻想文学22 特集・大正デカダンスで知ってから、ずっと読みたいと思っていた「幻影の都市」は文豪怪談傑作選(東雅夫編 ちくま文庫)の『室生犀星集 童子』に収録されている。
主人公は広告画や婦人雑誌に描かれた女に懊悩し、夜の街を徘徊する。遊郭、ヴァイオリンを弾く辻音楽師、浅草十二階とそこの落書きなどの風俗、大正浪漫ではなく大正の憂鬱が描かれている。今の人が読んでも共感できるのではないだろうか。 街で噂の電気娘がいる。触ると電撃が走るという電気娘の描写は奇妙で美しい。
かれの考えるところに拠るとこのふしぎな女の皮膚の蒼白さには、どこか瓦斯とか電燈とかにみるような光がつや消しになって含まれていて、ときには鉱物のような冷たさをもち、または魚族のふくんでいるような冷たさをもっているようにながめられたのである。
正体は白人とのハーフなのだが、大正時代には今よりも珍しかったのだろう。不当な差別もあっただろう。
思い出すのはホフマンの「砂男」だ。ストーリーが似ているわけではないし、「砂男」のナタナエルが自動人形オリンピアを求め狂気に至るのに比べると「幻影の都市」の主人公は電気娘にそこまでのめり込むわけではない。だが、浅草十二階での不安定な状態や電気娘の現実感のなさはなんとなく近い気がした。