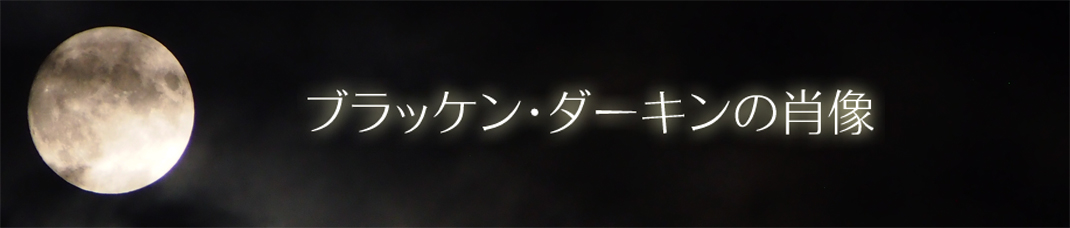『世界殺人公社』(ベイジル・ディアデン監督 1969)はスパイ映画ではないが、60年代スパイ映画のムードがあるコメディだ。同じく1969年の『女王陛下の007』でジェームズ・ボンドと結婚するトレーシー役のダイアナ・リグが世界殺人公社を追及する記者、ブロフェルド役のテリー・サヴァラスが新聞社社長、実は世界殺人公社の副代表、公社の一員に『私を愛したスパイ』(1977)の悪の大ボス、カール・ストロンバーグ役のクルト・ユルゲンスもいる。それだけでも007の雰囲気を感じさせるが、オリヴァー・リード演ずる公社の代表が変装したり秘密兵器を使ったりして、命を狙われながら、そして返り討ちにしながらイギリス、スイス、オーストリア、イタリア、ドイツ国境周辺と各国を移動し、公社を乗っ取ろうとする副代表の爆弾テロの陰謀を阻止するために奮闘する展開は、まさに007的だ。
オリヴァー・リードは『TOMMY』(1975)のときよりもややスマートで、濃い顔と芸風でヒーローを演じている。ダイアナ・リグは『女王陛下の007』のトレーシーも陰があってよかったが、『世界殺人公社』では非常にかわいい。好奇心旺盛で活発な役で、髪がブルネットで前髪があるからだろう。下着シーン、入浴シーンもあり。
原作のジャック・ロンドンがイギリスの作家と記載しているサイトがあるが、アメリカの作家だ。“The Assassination Bureau, Ltd”は1916年にジャック・ロンドンの死亡し、未完だったものをアメリカのミステリ作家ロバート・L・フィッシュが続きを書き、1963年に出版された。『野生の呼び声』や『白い牙』などで有名なジャック・ロンドンにこのような作品があるとは知らなかったし、意外だ。
原作は読んでいないが映画を見たかぎり、記者が世界殺人公社へ行くまでの過程や全体の雰囲気がスティーヴンソンの『新アラビア夜話』の「自殺クラブ」、アーサー・マッケンの『怪奇クラブ』を思わせるところがあったり、オスカー・ワイルドの「アーサー・サヴィル卿の犯罪」のような殺人にまつわるナンセンスな話であったりするので、確かにイギリス風ではある。
ギャグは強烈で、かなり笑った。何故、爆発シーンというものはこんなに面白いのだろうか。衣裳もセットもクラシカルで気に入った。ストーリーは放送したチャンネル関係者の方の記事参照。これから吹替えの放送もあるので楽しみだ。
飯森盛良のふきカエ考古学
私がこの手の映画の参考文献にしているのは、007を中心にそれ以外のスパイ映画を網羅している『危機一発スパイ映画読本』(洋泉社)、『オースティン・パワーズ』を中心に『007は殺しの番号』(1962)やその他スパイ映画とそれらに限らず60年代コメディを扱った『それゆけ!オースティン・パワーズ やっぱりボクらはおバカ好き!』(エスクァイアマガジンジャパン)だが、『世界殺人公社』はどちらにも載っていないから、やはりレアな映画なのだ。