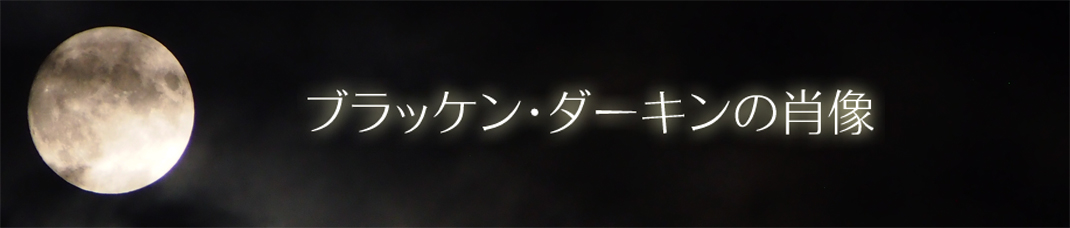先日、浅草に行った。上の画像は塔のあった方から撮った浅草六区だが、面白くもなんともない写真だ。昔の面影は何もない、というより、建物が全然ない空地が多かった。塔の跡地もヴィジュアル的に面白いものはなかった。
他の街ではなかなかない変わったことと云えば、暗いアーケードから入った狭い路地を歩いているとき、焼肉屋から一人で出てきた酔っ払いに声をかけられ、「ここすっげーうまい」と薦められたことくらいだ。だが、以前よりは古写真を方向感覚、距離感覚をもって見ることができるようになった。
旅のお供は『虹・浅草の姉妹』(川端康成 新潮文庫)だ。短篇「虹」、「浅草の九官鳥」、「浅草の姉妹」が収録されている。これも言葉狩りで狩られて新刊書店では売っていない。古本屋でたまたま見つけた。
昭和五年の『浅草紅団』は、とっ散らかった感じが猥雑な街を感じさせていいのだが、それから四五年経った「虹」は落ち着いた文体でひとつのレビュウ団という狭い世界を描いている。それは浅草への「別れの挨拶」であると、高見順は解説で書いている。
地下鉄の車掌だったのだが踊子にひっぱりこまれてレビュウ団員になった美少年木村がいて、踊の師匠になる決心が固い綾子、花形スター銀子、マスコット的な11歳花子など踊子たち、振付師中根、文芸部西林らの愛憎渦巻く、つかみどころのないふわふわした、しゃれた小説だ。『浅草紅団』は未完なのだが、「虹」の終わり方は無理矢理で、こうでもしなければ終わらなかったのだろう。ずっと作品世界の中にいたいような気分になる。
『虹・浅草の姉妹』のカバーのあらすじに、「浅草にオペラはなやかなりしころ、著者が親しんだカジノ・フォウリイの踊子たち━━体は早熟で艶めかしいのにどこか幼さを残していて、哀しい清潔さを感じさせる少女たちを描く「虹」」とある。よく読まないで書いたのか、勘違いしたのか、オペラはなやかなりしころは過ぎ去り、レビュウが流行していた頃の話だ。
『土地の記憶 浅草』(山田太一編 岩波現代文庫)は色々な時代、色々な人のエッセイが収録されたアンソロジーで、実際にレビュウの踊子だった望月優子の「紅団のあのころ」に川端康成との交流やレビュウ団の雰囲気が書いてあり、面白い。
彩色絵はがき、古地図が載っている『東京今昔散歩』(原島広至 中経文庫)を持って行き、十二階のあったあたりを歩いた。古い絵はがきをたくさん扱っていた神保町のアベノスタンプが閉店していてショックだった。