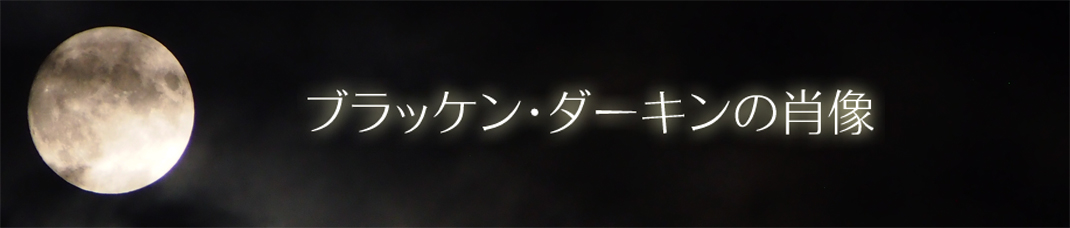短篇を色々読もうと思っていたが、アーサー・マッケンの「パンの大神」(1894)で引っかかった。登場人物や視点が交錯していて一度読んだだけでは把握しきれず、すぐにメモをとりながら再読した。過去の記事「『夢の丘』 アーサー・マッケン 田舎にも都会にも馴染めず死に向かう芸術家」に書いた「最後まで読んだら、何だかよく分らないけど何か凄いことは分かった」と同じ感想だ。
Amazonの洋書のレビューでも”difficult, but well worth it”とあり、英語ネイティヴでも難しいようだ。「パンの大神」が収録されている『怪奇小説傑作集1』(創元推理文庫)の解説では「脳の手術をうけた少女が、その後パンの神と通じて淫楽の化身となり、多くの男性を淫楽のとりこにして殺していく話」となっているが、その少女については具体的に書かれていないので、何が淫楽なのかよく解らない。パンが淫欲の象徴というのは何となく知っていたものの、より深く調査する必要がありそうだ。冒頭にある脳の手術をする、かなりのマッド・サイエンティスト、ドクター・レイモンドは少ししか出てこない。タイトルに書いた「男を破滅させる謎の女の正体」は自分で想像するしかない。
『怪奇クラブ』(アーサー・マッケン 創元推理文庫)の解説によるとH・P・ラヴクラフトはマッケンを賞揚していて、「パンの大神」の魅力はサスペンスを累々層々と最後の恐怖まで積みあげていく語り方にあり、物語は魔力に富んでいると書いている。
19世紀末ロンドンの街の暗部、二面性、本や骨董談義、科学、医学、犯罪の当時の雰囲気が「パンの大神」にもある。