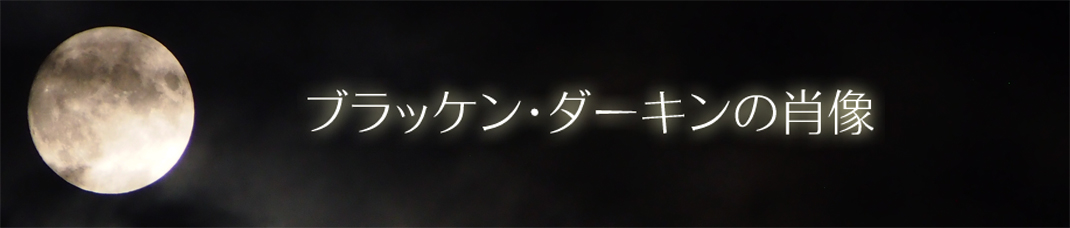『死都ブリュージュ』(ローデンバック 1892 岩波文庫)を読んだ。重版のときに、予備知識はなかったが表紙の絵とあらすじに惹かれて買ってあった。上の画像の人物は著者であって、小説の主人公なわけではない。だが、憂愁を帯びた瞳が小説の雰囲気に合っている。陰鬱な都市、鐘の音の描写に美しい比喩が多い。
妻を失い、打ちひしがれ、街をさまよう男ユーグが、妻にそっくりの踊り子ジャーヌに出会う。その場面はスローモーションのようだ。ユーグはジャーヌにのめり込んでゆくが、家政婦バルブは信仰心の篤い人物で、主人の行動を快く思っていない。
半分も読まないうちに、この主人公は強烈に打ちのめされることになるだろうことは予想がつく、まさに19世紀末デカダンスだ。亡き妻を再現しようとする男の思い込みは身勝手なものだが、全ての人間関係は思い込みや勘違いだ。求めた理想は少しづつずれ、着々と破滅へと向かっていく。
訳の窪田般彌は『生きている過去』(アンリ・ド・レニエ 1905)も訳していて、『未來のイヴ』(ヴィリエ・ド・リラダン 1886)の解説を書いている。