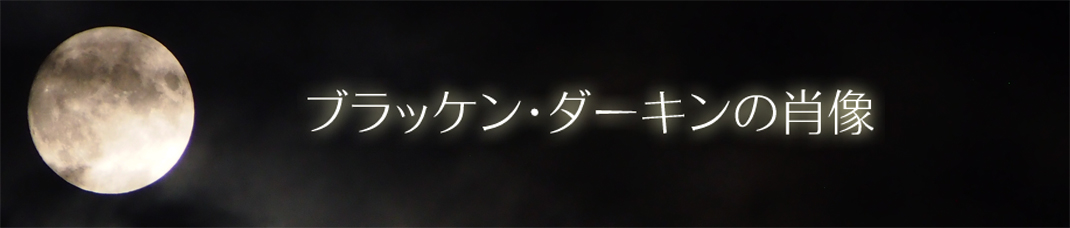アーサー・マッケンの『夢の丘』(1907)は、以前読んだときは中断した。ほぼ全篇、文学者志望の男の妄想でストーリーらしきストーリーも会話もなく、読みづらい。これは作品が悪いのではなくて、私の想像力が衰えているせいだろう。好きか嫌いかと云えば好きなのだ。
最近読んだ『一九三四年冬━乱歩』(久世光彦 1993)のモチーフになっているので、きちんと読もうと思った。江戸川乱歩自身が『夢の丘』のような都会のロビンソンに憧れたし、作家のスランプという点で『一九三四年冬━乱歩』と共通している。最後まで読んだら、何だかよく分らないけど何か凄いことは分かった。
田舎での少年時代、ルシアンはスポーツよりも文学を好み、就職するよりも小説家になることを望む。そういう人は変人のように見られる。芸術家から見れば村の人々の方が俗物なのだ。都会に出て、孤独な創作活動を続ける。意欲はあるのだが、なかなかうまくいかない。少年時代に見た赤光に燃え立つ山奥の丘の光景や、街のお祭り騒ぎで声をかけてきた女、古いあばら家から妄想が広がり、狂気に至る。
遺産も入り、生き方上手なら狂死することもないのに、幻想に嵌って行ってしまう人種もいる。冷静なときに読めば悪い方へ行き過ぎだろうと気づくのだが、そういう時期もあることは分かる。紀田順一郎の解説によれば、アーサー・マッケンは同時代から取り残されたが、現実との絶望的な疎外感に悩む人々の共感を獲得した。私も生き方上手よりはルシアンのような人物の方に魅力を感じる。