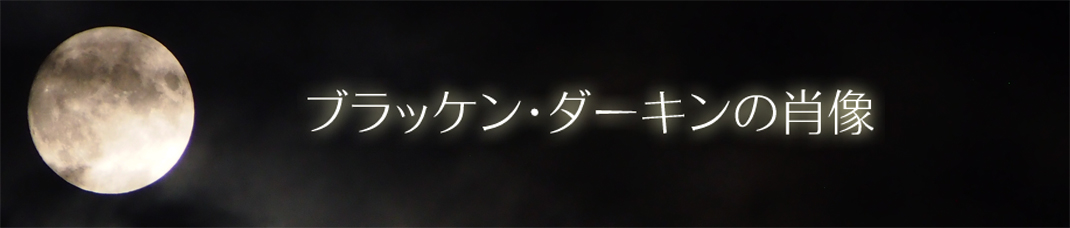ブライアン・ギルバート監督『オスカー・ワイルド』(1997)を見た。ワイルド役は私の好きな映画『ピーターズ・フレンズ』のピーター役スティーブン・フライ、愛人ボジー役はジュード・ロウ、ほんのチョイ役でオーランド・ブルームが出ている。ワイルドは若いときは痩せているとは云わないまでもまだスラリとしていて晩年は肥ったが、映画では最初からちょっと太めだ。
新潮文庫の『ドリアン・グレイの肖像』の佐伯彰一の解説に、ワイルドは意外なほど生真面目なモラリストだと思われたと書いてある。これを読んだとき、そうなのかな、表面的にはモラリストぶっているけど実際はデカダンなヴィクトリア時代の倫理観をおちょくっているんじゃないのかなと思っていたのだが、映画を見ると、やはり生真面目なモラリストなのかもと思った。ボジーに翻弄され、ボジー父子の確執にハメられた人のいい芸術家という感じだ。
あまり気にしたしたことがなかったワイルドの母親が映画では個性的に描かれている。ワイルドは受け身で若い男にモテモテだ。ラストはあっさりしているが、実際はもっと悲惨だった。
私がワイルドを好きになったのは『ドリアン・グレイの肖像』を読んで気に入ったからだ。面白いアフォリズムがたくさん出てくるし、恋愛もの、サスペンス、ミステリー、ホラー、ゴシックロマンスなど何でもありのエンタテインメントが美しい言葉で語られ、色々な感情や心理が渦巻いている。
私の好きなところはドリアンが恋人、女優のシビルについてヘンリー卿に話すところだ。
「今夜、あのひとはイモージェンになる。あすの晩はジュリエットだ」
「それじゃ、いつシビル・ヴェインになる」
「決してならない」
「それは乾杯ものだ」